
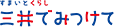


「しばらく放っておいて」
彼女からLINEが届いたのは、家まであと5分のタイミングだった。
高円寺の駅から徒歩15分。住宅街に突如現れるエスニックな雑貨屋の隣に、1LDKで11万3000円の僕らの家があった。
辺りは街灯も少なく、秋の夜には少し心細さが残るほど暗かった。
「ごめん、10対0で俺が悪いです」
彼女がスマホを手放す前にと思い、慌てて短い謝罪文を送った。が、既に遅かったようで、既読は付かない。
「でも本当に悪気はなくって」
未読。
「もうすぐ家に着くから、ちゃんと説明させて?」
またしても、未読。
完全に怒らせてしまったようだった。
金曜の夜にも関わらず、彼女は昇進がかかった試験のために勉強をしていた。ストレスも溜まっていたのだろう。休みの合間に送ってくれたLINEを、僕が見事にスルーした。スルーしただけならまだしも、ほぼ同タイミングで、同僚の女性と飲んでいるツーショット写真をSNSにアップしていた。このタイミングの悪さが、彼女の逆鱗に触れた要因だった。
「私がどれだけ苦しんでいても、あなたの仕事に一切関係のないことぐらいわかるよ。でも、彼女が苦しんでいるときに、これみよがしに異性とのツーショットをアップするって、それ、どういう神経してんの?」
必死に謝罪を試みたが、もう聞く耳を持たないし、LINEを見る目もないようだった。仲直りのケーキを買ったところで美味しいと思う味覚もなさそうだし、五感のほとんどが閉じられていることを悟った。
昔から嘘や言い訳が下手だった僕と、一度怒ると怒鳴るより黙る方を選択する彼女との喧嘩は、ここにきて史上最大の山場を迎えた。

そもそも、どうして中目黒ではなく、高円寺に住んだのか。
半年前、僕らは初めての同棲に向けて作戦会議をした。
そこで彼女は中目黒に住むことを熱望し、僕はそれを予算内であれば構わないと認めた。
しかし、現実は厳しく、11万の予算で中目黒に1LDK物件を探すのは、なかなか難しかった。具体的に言えば、4つの賃貸紹介サイトと3つの不動産会社を駆使して2カ月粘っても、「中目黒・11万・1LDK」で自分たちが気に入る物件が見つからなかったのである。
「じゃあ、祐天寺は? あそこも、若い人には人気じゃない?」
「やだ。せめて代官山。あとは、恵比寿とか」
「ほんと、いちいち脳内が華やかだよなあ」
「うるさいなあ。住む場所って大事だよ? 起きたらハッピーな気分になれる場所に住みたいじゃん」
「じゃあ、ミラコスタは?」
「それはいいね。ミラコスタに住めたら毎日プロポーズでもしてくれるわけ?」
そんなやりとりの末、徐々にお互いが妥協して行きついたのが、「高円寺・新築デザイナーズ物件・11万3000円・1LDK」だった。


「当初の予定からだいぶ離れている」とお互い言いながらも、内見のために久しぶりに訪れた高円寺は、中目黒ほど洗練された街ではないものの、個性的な飲食店や雑貨店、古本屋が立ち並び、カルチャー色が強く残っていた。未だに若者に人気な土地であることはすぐにわかった。そして何より、中目黒に比べれば家賃相場も安く、現実的に見てふたりで住むには適した場所だと判断された。
彼女は高円寺という土地に最後まで納得していなかったものの、デザイナーズマンションなのに収納が多いことと、ひたすら天井が高いところに惚れた。僕は僕で、駅から15分は遠いと思うものの、玄関が広くて、コンロが3口であり、コンセントが多いことに喜んでいた。
「人生に妥協はつきものだからね」と、最後にはあっけらかんと受け入れたようすが、やたらとかわいかった。彼女の機嫌が良ければ僕の人生もそれなりにハッピーだろうと思い、この物件に落ち着いた。

そして、引っ越してから約半年が経った今、僕らはひとつの修羅場を迎えていた。
家に帰ると、彼女の姿がなかった。
これまでも些細な喧嘩ならしてきたが、出て行かれたのは初めてだった。
リビングに、キッチンに、脱衣所に、寝室。
とりあえず家の中を一通り回って、置き手紙らしきものがないかを探したが、当然何も見当たらなかった。念のため風呂場まで見返してリビングに戻ってきたところで、彼女が勉強していたであろうローテーブルの下に、彼女のスマホが落ちているのを見つけた。
これで未読のままだった理由はわかった。スマホを持ってないとなると、尚更ピンチだった。
頭が冷静になってきたところで電話でもすれば、仲直りのきっかけこそ作れるかもしれない。でも今夜は、それすら許されないようだった。断固たる決意を感じた。
「待つ」か、「探す」か。
二択だった。それも、ドラマや映画じゃないから、探したって簡単に見つかるようなものじゃないし、現実的に考えればほぼ一択だった。闇雲に探すよりも家で待っていたほうが再会の確率は高い。
でも、冷静に考えて、こういうときこそ彼女は、ドラマや映画のようなアツい展開を望むタイプだった。たとえ見つけてもらえる可能性が10パーセントを切っていたとしても、必死に探してくれるような男にこそ、惚れ込む女だった。
「しょうがない」
行き先は、わからない。
それでも、家を飛び出すしかなかった。

「なんで、バレんの」
探し始めて30分後。彼女を見つけたのは、「近くのローソン」「西友」、「初めてふたりで外食したカフェ」「駅の改札」という勘を全て外した末に、「ここはないだろう」と思いながら寄ったさびれた公園だった。
きょとんとした顔でこちらを見つめる彼女にスマホを渡しながら、できるだけ格好つけた言い回しを考えて、息を整えながら質問に答えた。
「夢見がちな女性が彼氏と喧嘩したとき、どんな場所にいるときに彼氏に迎えに来てほしいかを考えたら、“さびれた公園のブランコ”か“滑り台の上”しかないって、会社の上司が言ってた」
「なにそれ」
目線は下を向いているが、クスリと笑うのがわかった。
「近くにブランコがある公園って、ここしか浮かばないじゃん。前にここで線香花火したの、懐かしい」
「そう。それをちょうど、思い出してた」
思いのほか、穏やかな表情だった。こうして迎えに来た時点で、もう同僚との写真については、気にしていないようにも思えた。
「で、あの女は誰なんだっけ?」
……勘違いだった。まだ思いきり、根に持っていた。
「だから、同僚で」
これでもかと言わんばかりに、反省の色を全面に出した声で答える。
「単なる同僚?」
「はい、“単なる”です」
「どこまで“単なる”なの?」
「それ、どういう意味?」
「飲みに行っただけ? 手はつないだ?」
「つながないってば。それのどこが、単なる同僚なの」
「じゃあ頭ポンポンは? したでしょ。あんた、それ好きだから」
「してないってば」
思わず笑って否定する。笑って否定するが、こういうときは笑うべきなのか、真面目な顔をすべきなのか、いくつになってもわからない。
「じゃあ、何もなかったんだ」
全てを見透かすような目で言われた。
実際、前も冷蔵庫にあった彼女のぶどうゼリーを食べたとき、この目で見透かされた。
「うん、絶対に、なんにもない」
1ミリも目を逸らさないようにしながら、ゆっくりと事実を答える。いま動揺した素振りを見せれば、この公園からあと2時間は帰れないだろう。
「ちゃんとしてよね」
ブランコから降りながら、低いトーンで忠告してくる。
「男女はね、疑われた後のケアよりも、疑われないようにする努力が大事なんだよ」
「はい」
「疑われてんじゃねえよ」
「ごめんなさい」
差し伸べられた手を握ると、痛みを感じるほど強く握り返された。

「帰るよ。同じ家に住んでるんだから、帰ったらもう、今夜の話はナシね」
「うん」
「でも、忘れたら殺すからね」
「はい」
油断も隙もない。
この半年で、彼女はずいぶん僕の扱いが上手くなった。
僕はそれに甘え過ぎることなく、生きていかなければならないと思った。
街灯の少ない高円寺の住宅街を、ふたりで並んでゆっくりと帰った。