
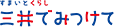

人の体って、死んだ後もけっこうずっとあったかいんだな。
というのが、17年間生きてきて、初めて人の死に立ち会った直後の俺の感想だった。
はあ、と荒い息を吐いて、ごろりと横になると、暗くて広い板天井が目の前に広がった。
シーツは汗でぐっしょりと湿っている。
人の体から、短時間でこれだけの液体が出るというのが面白かった。
隣では同じように息を弾ませ、熱い鞠のような柔らかい物体が、どっくんどっくんと波打っている。
女の子の体だ。
じいちゃんが死んでから三カ月。俺がしたことといえば、遺品を整理したことと、今まで通り学校に行くこと。
それから人生初めて女の子と一緒に横になって寝ている。それだけだ。

「えーっ、リョータ君ってひとりでこの家に住んでるの?」
女の子が声を上げる。同じクラスの子だ。じいちゃんが死ぬまで、喋ったことなんて一度もなかった。葬式で学校を休んだ俺を心配して話しかけてくれて、それから仲良くなった。
女の子の体は、男の体よりもよく光をはね返す気がする。発光塗料が塗られているみたいに、暗闇でもかすかに白く発光してみえる。
「うん。前はたくさん、居候がいたんだけど、ここ1年は俺とじいちゃんだけだったし」
この家の最後にして最長の居候、マヒコ兄ちゃんは昨年結婚して出て行った。最近、なんかの小さな文学賞をとったらしい。急に忙しくなり、めっきり遊びに来なくなった。
「そっかあ」と女の子は神妙な声で呟く。さっき、うちに上がったときにはキョロキョロしながら「こんな大きなお家に上がるの初めて」と言っていたっけ。
「ひとりで寂しくない?」
うーん、と言って俺は天井を見つめる。じいちゃんがいなくなったこの家は、2人で住んでいたときよりも一回り大きく見える。脱皮したヘビの抜け殻みたいだ。
ガラス戸から吹き込んだ風が吹き抜けて、体が冷たい。
「そうでもないよ。けっこう気楽だし。ご近所さんとも、付き合いあるし」
俺の最愛のじいちゃん、戸塚タカシ(享年82歳)は、今年の5月25日、うららかな午後の日差しの差す中、亡くなった。じいちゃんの能天気な性格を表すような、ぽかんとした死だった。
病室にはたくさんの知り合いが詰めかけて、穏やかなムードでの最期だった。
俺は少し泣いたけど、正直、全てを納得した上での温かな涙だった。じいちゃんは、ゆっくり、丁寧に、時間をかけて死んでいったから、話したいことは全部話せたし、俺の方で思い残すことは何もなかった。悲しみ以外の成分が入り混じる涙を流したのは、17年間のこれまでの人生の中で初めての出来事だった。
じいちゃんは俺が子どものころ、銭湯を経営していた。いろんなことがあって閉店したが、近所の人々からの要望や、当時、住み込みで働いていた居候たちの助けもあって、建家だけは残すことにした。今は足湯施設のあるカフェ兼ギャラリーとして運営している。寺と神社と猫と坂ばかりのこの街ではなかなか貴重な文化的施設らしく、足を運んでくれるお客さんは多い。
今でも銭湯の常連さんだったおばあちゃんが、ふらりと家の軒に立ち寄って、昔の思い出をにこにこしながら話してくれる。じいちゃんの銭湯が、どれだけ街の人たちに愛されていたかが良くわかる。

「このお家に、ずっと住むの?親戚とかは?」
「今のところは、このままでいるつもりだけど。叔父さん夫婦と、関係が良いわけじゃないからね」
「ひとりになって、困ってることとかない?」
「別に。俺、じいちゃんとふたりのときからずっと身の回りのこととか自分でしてたし、それまでだって、ずっと自分のことは自分でやりなさい、って言われてきたから」
この子の家族構成はどんなだっけ……と思い出そうとしても、脳が働かない。
「うちさあ、昔から人の出入りが激しかったんだ。じいちゃん、居候を住まわせるのが趣味みたいなとこあったから。みんな、よくしてくれたけど、出て行くときはだいたい、あっさりしてんだよね。また遊びにくる人の方が少なくてさ。……だから、今ひとりになったからって、別にどうってことないかも。人はみんな、いつか、どっかに行っちゃうもんだって思ってるし、そもそも、もともと俺、両親と離れて暮らしてたから」
そんなことよりも、俺の今の関心事は、もっとずっと、違うところにあった。
正直なところ、このがらんとした家にひとりになって、困っている。
生活に困っているのではない。自分の取り扱いに困っているのだ。
気を紛らわせたくて、別の生き物を連れ込んだものの、今は、早く帰ってくれないかな、という気持ちになっている。
「……そんなだからさ、進路が決まるまでは、とりあえず、この家にいるよ」
不意に、ふええと赤ん坊のような声が耳元で聞こえたので俺はびっくりして体を離した。女の子が泣いている。わざとらしいくらいに大げさな動きで俺にしがみついてきた。
熱い液体が脇腹あたりを湿らせる。
「リョータ君、かわいそう」
気だるさのなかに、別のものが入り混じり、キン、と脳の芯を冷やしてゆく。
「たったひとりで、これまで頑張ってきたんだね」
空になったばかりの体の内側に、もやもやとした澱が淀みはじめ、たちまちいっぱいになる。俺はそれを、必死で追い出そうとする。頭では必要ないと、わかっているから。
「困ったことがあったら言ってね。なんでもするから」
だったら、今すぐ帰ってくれ。
そう言いたいのをぐっと飲み込んで、俺は女の子の頭に手を回す。どうして俺が慰めているのだろう。
「ごめん、眠いからちょっと寝るね」
眠気を装い、そっと目を閉じた。女の子は、自分の言葉に俺が安心したと勘違いしたらしい。満足そうにくっついてくる。
そのうち、本当に熱くぬるりとした眠りの底に落ちても、その言葉を留めた脳の芯だけは、しこりのように硬く凝っていた。

ここに来て最初の記憶は、素っ裸で、たったひとりきり、がらんとした高い高い天井を眺めていたことだ。
「あんときはよう、お前、真っ赤っかのすっぽんぽんで、茹でタコみたいだったんだぞ。それが入り口からよう、ピューッと飛び出して来てよう、俺は腰抜かしたね」
近所に住む大工のマサさんは、うちの縁側にふらりと立ち寄っては、そのときのことを500倍は大げさに話す。
俺は、捨て子だ。
実の親に、祖父の経営する銭湯に置き去りにされた。
母親とは、あれから一度も会っていない。
あーお、あーお、という飼い猫の声で目が覚めた。
いったい何時間寝たのだろう。灯をつけない家の中は真っ暗だ。
女の子はすでに消えていた。
玄関の鍵を閉めに、俺は裸のまま廊下に出た。
途端にギョッとした。真っ暗な三和土に、誰かが立っている。
――強盗か!?
その男は初秋だというのに、ふかふかのカーキのジャケットに、でっかいエスキモーみたいなブーツを履いている。ざんばら髪に無精髭。荒々しいなりのわりに、顔立ちは端正で、どんな景色にも馴染みそうな透明感がある。
そう、まるで、幽霊みたいな。
男は俺を見ると、ニカッと笑った。
見る者全員を惹きつけるような、それでいてどこにも連れていかないような、そんな笑みだった。
「リョータ、なかなかやるじゃん」
俺はぽかんとして、相手を見た。
「女の子、俺と入れ違いにさっき出て行ったよ」
違う。そうじゃない。俺が気にしているのはそんなことじゃない。
お前は一体、誰なんだ。
「だ」
喉がカラカラでうまく喋れない。しわがれた声は無様に途切れる。
「れですか」
言った途端に、違う、と感じた。
俺は、こいつが、何者であるかを、すでに知っている――……
男は、ニィとさらにもう一回り大ぶりの笑みを浮かべて言った。
「アキラだよ。お前と昔、一緒に住んでた」
記憶が急に揺れ起こされ、心臓のあたりの細胞がばたばたと暴れる。
「大きくなったなあ、リョータ」
俺は自分が裸であることも忘れて、そこにしばらくの間、突っ立っていた。
こうして、俺とアキラの2度目の共同生活がスタートした。
誰かと暮らし始めるのって、生活の中に新しい絵の具が足される感じだ。
これまでたくさんの人間と一緒に暮らしてきたけど、こいつの色はトクベツな感じがする。
透明に近いブルー。柔らかくて、けど、決してこの家に残された、他の人間たちの色とは決して混じり合わない。
「あー、やっぱり日本のカップ麺って美味しいよなあ」
うちに転がり込んできた日の夜、アキラは居間のちゃぶ台であぐらをかき、俺のカップラーメン濃厚豚トリュフ味を豪快にすすりながら言った。
「手紙がさ、届くのが遅かったんだよ。俺、通信手段何も持ってないからさ、近所の村の郵便局に行かないと、手紙も受け取れないの」
「今まで、どこにいたんすか」
「アラスカ」
アキラはラーメンの汁をずず、と吸うと言った。
俺はあっけに取られる。
「アラスカで、クマと相撲とってたんだ。このブーツも、ジャケットも、俺が作ったんだぜ」
……こいつ、本当にこんなやつだったっけか。
記憶の中の彼はもっと、なよっちくて、控えめで、女みたいなやつだった。一緒に住んだのは半年くらいだったけど、それでも優しくしてもらったことは覚えている。こんなふうに、俺のカップ麺をガツガツ食いながら、ヒゲだらけの顔で笑うようなやつじゃなかったはずだ。
アキラはいつまで居るとも言わない。
別に俺も、居られて困ることがないので何も聞かない。
むしろ、いてくれて助かっている。
家事は慣れているつもりだったが、実際にひとりになってみると大変で、何日も放りっぱなしだったこともあったから、手伝ってもらえるのは助かる。ギャラリーの方の業務も、俺が学校に行ってる間にアキラがやってくれているので気が楽だ。
勝手知ったる我が家、とでも言うような彼の身のこなしを見ていると、ああ、本当に、あのアキラが7年ぶりにうちに戻ってきたのだなあ、という実感が湧いてくる。
アキラは決まって食事の後に、じいちゃんの家に向かって頭を下げる。紙を刀で切るように、体の中心にすっと引いた線を、頭頂でなぞるように、潔く、静かに。
その動作があまりにも綺麗で、俺は毎回、見とれてしまう。男にも、お辞儀にも、そんなふうに感じたことなんて、17年間生きてきて初めてだ。
こいつがどうやって7年間過ごしてきたか、詳しくは聞いてない。
話してもらったところで、実感も湧かないだろう。
けど、その姿を見ていると、馬鹿な俺でもわかる。
俺の知らない7年間を、こいつは、生き抜いてきたんだってこと。
それは、俺にとっての、俺がこれまで生き抜いてきた7年間と同じように、こいつにとっては同じだけの重みと体積をもつのだってこと。
一度、アキラに聞いたことがある。
「一緒に住んでた人たちに、帰国したことを伝えようか?」って。
そしたらやつは首を振って「いいよ。特にはしなくて。会えるときには、会えるから」と言った。
アキラみたいに、でかい世界を見たら、小さいことで悩まなくなるんだろうか。
その気持ちがわからないことを、時折、歯がゆく思う。

「なんなんだよ、これは」
「はあ」
窓から斜めに西日の切り込む教室は、半分は昼、半分は夜で、エッシャーのだまし絵みたいだ。
「お前ね、これでいいと思ってんの」
目の前の教師は苛立たしげに指で机を叩いている。
進路指導室の机の上に広げられているのは2週間遅れで提出したくちゃくちゃの進路希望届だ。
「むしろ、何がダメなんすか」
うちに以前住んでいた、プログラマーのゴスピから本格的にアシスタントとして修行しないかと持ちかけられたのは、つい2週間前のことだ。
子どものときから、彼にプログラミングを教えてもらっていたおかげでいっぱしの専門学校生くらいには知識もあるし、今も、彼の仕事をちょいちょい手伝っている。
別にものすごく好きってわけじゃないけれど、特にやりたいこともない、今の俺には一番わかりやすい選択肢だった。
「『知り合いに弟子入り』ってね、お前。……いや、別にダメじゃないけど、もう少し考えた方がいいんじゃないの。進学は大事だぞ。お前、頭もいいんだし、勿体無いだろ。もっと将来の選択肢を増やしてだな」
教師は夏が戻ってきたみたいに大量に汗をかきながら小さい口をモニョモニョと動かしている。
「おじいさんが亡くなって大変なのはわかるけど、おじさん、進学費用出してくれるって言ってるんだろう」
そんなのは建前だ。本当は出したくないに決まっている。それに、俺がその申し出を受け入れた場合、最初に来る交換条件は「刻の湯ギャラリー」の解体と土地の売却であることは明白だった。
「進学したら、うちのギャラリーを運営する人がいなくなるし、昼も家にいられなくなるんで」
「そうだけどさ、長い目で将来を見て考えてさあ」
「考えた上で、これですけど」
「……もっとさあ、他にやりたいこととか、ないのか。将来の夢とか。先生、応援するぞ」
わかっている。こいつは生徒にわかりやすい“青春”を謳歌させたいのだ。プラス、自分にとって都合のいい道を。
「……先生はうちの学校の進学実績を増やしたいだけじゃないっすか」
先生はうろたえた顔で俺を見た。わかりやすい。
「確かにうちはまあまあの進学校だし、別に勉強したくないから就職するわけじゃないっすよ。……けど、別に、やりたいことがないからとりあえず手に職つけるってのも、アリじゃないっすか」
日の陰りは濃くなり、吹奏楽部のホーンの音色が窓の外の茜色の空に響く。そろそろ、帰してもらえないだろうか。
先生ははあ、とため息をつくと
「まあ、お前んちが特殊なのはよくわかってるけどさ……」
と言って目を細めた。
「もうちょっとフツーの進路も視野に入れてみたらどうだ」
俺はかばんを引っ掴んだ。何も言わずに立ち上がり、教室の出口に向かう。
相手も慌てたように立ち上がり、「あ、おい」と叫ぶ。
「……うちが特殊って、どういう意味っすか」
「あ、いやあ」
歪められた口元が、苦し紛れに弁解を吐き出す。
「別に悪い意味で言ってるわけじゃないぞ……ただ、普通じゃないことは、普通じゃない、だろ」
俺は、バァンと音を立ててドアを閉めて教室を出た。

屋根の隙間から溢れ出る夕陽の光線が、雨で濡れた道の上に光の川を作る。
歩き慣れた商店街の道を、俺はとぼとぼと歩いた。
子どものころから、じいちゃんや居候の人たちと、ずっと歩き慣れた道。
俺はこの街が好きだ。
ここで過ごしてきた俺の人生だって、そんなに悪いものじゃない。
……そう、いつもだったら素直に思えるのだが、今日はさっきの担任の顔がちらついて、うまく、その解にたどり着けない。
“「普通じゃないことは、普通じゃない、だろ」”
わかってる。彼らに悪気がないってことが。“普通の側”で生まれ育った人間にとっては、それを臆面なく口にすることは、むしろ「自分は差別的ではないですよ」と表明するためですらあるのだ。
けど。
彼らが何の気なしに口にする、その一言の裏にある透明な視線が――語られない胸のうちの「かわいそう」が、いつも俺の心臓にぺたりと張り付いて、皮膚呼吸を止める。
言い返すようなことじゃないから、余計に。
「リョータ君、かわいそう」
……あの女の子の言葉が頭の中にリフレインする。
かわいそうってなんだろう。
かわいそうって、不幸ってことか。
両親がいなくて、じいちゃんしか知らなくて、大学は行けるかわかんないけど、プログラミングは少しできて。ご近所さんや、うちの居候だったたくさんの人たちに囲まれて育って。今もこうして、ひとりで生活できている。
そんな俺は、不幸なんだろうか。
「家族」が一緒にいない人間は、だめなやつなのだろうか。
どんなふうに育ったところで、「正しい家族」がいないやつは、不完全なのだろうか。
ひとりぼっちはだめで、誰かと一緒にいることを求めたほうがいいのだろうか。
そうするべきなのだろうか。「社会」のために。
家に帰ると、アキラはいなかった。
やつがここにきて一月、普段は家にこもりっきりのくせ、時々ふらりとどこかへ行って1、2日帰ってこない夜がある。
そんなときはなんだか、家全体がスカスカになった気がする。
3カ月かけて、人のいない家にやっと慣れたというのに。
藍色に陰った坪庭からは、すでに虫の声が響いている。
こんなに静かな夜は久しぶりだ。
電気のつかない和室に敷きっぱなしの布団の上に寝転がった。
手を天井にかざし、自分の手のシワを目でゆっくりと追う。
俺は自問自答する。
「俺よ、俺は不幸ですか」
鈴虫の鳴き声しか聞こえてこないと思ったが、
胸の内側から、予想外に誰か知らない男の声が響いてきた。
“すげー幸せでもないけど、
すげー不幸でもない”
俺は安心して、瞼を閉じた。
今、考えるべきことは、じいちゃんから受け継いだこの家と、刻の湯ギャラリーを潰さないことだ。

通りの並木がオレンジ色の葉を、秋風に揺らしている。
隣の民家の生垣の向こうからは、栗を焼く甘い匂いがする。
もうすっかり秋だ。
休みの日、俺はぼうっとギャラリーの前を掃除していた。
「リョータ君!」
聞き覚えのある声で呼ばれて顔を上げると、ショートカットの背の低い女の子が手を振っていた。
「ハルちゃん」
ハルちゃんは別府の温泉協会の会長の一人娘で、俺よりも4つ年上だ。
建物の老朽化や継ぎ手などの問題で閉館した温泉旅館や銭湯を、なんとか温存しようと、商業施設やイベントスペースに改築し町おこしを行っている。
「刻の湯」のことも、数年前にSNSで探し出し、尋ねて来てくれた。それ以来、東京に遊びに来るときには必ずうちにも立ち寄ってくれるのだ。
「タカシおじいちゃんのこと、この度は御愁傷様でした」
ハルちゃんは深々と頭を下げた。おかっぱ頭のうなじが清々しい。
「いえいえ。わざわざありがとう」
そのままギャラリーの前でたわいもない世間話をした。こうやって、遠くから足を運んでくれる人がいることも、じいちゃんの銭湯を残しておいてよかったと思うことの一つだ。
話が途切れたところで、ハルちゃんはふと思い出したように「そうだ」と言った。
「リョータ君てさ、別府に親戚、いる?」
「え?どうして?」
「うちの温泉によく来てくれるコンパニオンさんでさ、戸塚さんって人がいるんだけど。その人がリョータ君にすごく似てるんだ。だから、親戚かなって」
心臓が、跳ねた。
「下の名前は、多分、源氏名だと思うんだけど。一回、事務所の人に戸塚さんって呼ばれてるのを聞いてさ」
うるさいくらいに、心音が耳に届き始める。
「40代半ばくらいなんだけどね。すごく美人なんだよ!」
「……いや、うち、東京にしか親戚いないし」
皮膚が粟立つのを止めようとしながら、なんとか答えた。
「違うと思う」
「そうだよね、関係ないよねー」
彼女はすぐに他の話をし始めた。
俺の耳は、さっき聞いた言葉が入り口を塞いだように、外界の情報を受け付けようとしない。ぐるぐると、様々な情報が頭の中で暴れまわる。
ハルちゃんが喋るのを眺めながら、俺は、彼女が早く帰らないかな、とぼんやり思い始めていた――。
(後編に続く)
じいちゃんが亡くなり、少しずつ新しい生活を始めたリョータ。そんな中で突然聞かされる、自分と似ている女性の存在……“戸塚さん”とは一体何者なのだろうか――。後編では、リョータは将来のこと、刻の湯のこれからについて。そして「家族」の意味について考えていくようすを描いていきます。