
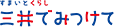

パン、と気持ちのいい音を立てて、白いシーツが空の下に広がる。
アキラが洗濯物を干している。俺はそれを、縁側に寝転んで見上げる。
白い布越しに、青い、青い、目に突き刺さるような碧空が見える。
“「うちの温泉によく来てくれるコンパニオンさんでさ、戸塚さんって人がいるんだけど。その人がリョータ君にすごく似てるんだ。だから、親戚かなって」”
実をいうと、俺がずっと気にかけていたのはこのことだったのだ。
ハルちゃんが帰った後、俺はSNSでひたすら検索した。
#別府温泉 コンパニオン
#別府 ●●温泉
およそ想像しうる限りのキーワードを入力した結果、やがて一枚の写真にたどり着いた。
見知らぬ誰かがアップした社員旅行の宴会の写真。どこかの旅館と思しき場所で、コンパニオンと客がくっつきあって写っている。赤ら顔のおじさんたちの中、一人だけ、着物を着た女の人が紛れている。
じいちゃん似の細くて高い鼻。
巻貝のように、ぴょこんと上を向いた、印象的な耳。
俺の頭の両側についているのと、全くおんなじ特徴の。
困ったような作り笑顔で、目の焦点はあってない。フラッシュに驚いたように見開かれ、その中に赤い光が点っている。
少しグレーがかった髪。痩せた肩。
記憶を手繰り寄せる必要もない。
直感が体の芯からやってきて、この人だと告げる。
――彼女は、実の父親が死んだことも知らない。
子どものころ、母さんが親父と喧嘩して、家ん中がめちゃくちゃに破壊されるたびに、俺は洗面台の棚に並ぶ化粧品セットを眺めていた。
母さんはいっつも、お金がない、という割に、高級な化粧品を揃えて使っていて、何かあって家を出るときには決まって、前日の夜にそれが棚から全部消えていたのだ。今から思えば、それは「止めて」のサインだったのだろう。いつか、俺だけが置き去りにされて、あの人は永遠に、化粧品セットと共に消えて無くなってしまうんじゃないかと不安だった。
実際、置き去りにされたのはそのとき住んでた大阪のアパートじゃなく、じいちゃんの経営する銭湯だったけど。

「なあ、リョータ、七輪で秋刀魚焼かない?」
気がつくと、アキラが真上から俺を見下ろしていた。青い空が人の形に陰る。
「昨日、コタツ出したときに見つけたんだ」
アキラは昨日、納戸の中からコタツを引っ張り出してきた。「早くないすか」と聞くと、彼は「やっぱうちにはこれかなと思って」と言って笑った。
「サンマの他にさ、燻製も作ろうと思って。お前、食べるだろ」
炭に火をつけ、スーパーで買って来たサンマを網の上に並べる。
パタパタとうちわで扇ぐと、チラチラと炭の火が明滅する。そのうち、香ばしい匂いが漂ってきた。
「アキラさんはさ」
俺は彼の後ろ姿に話しかける。
「ずっと会いたいけど、会えずにいる人っていますか」
アキラの手が一瞬止まる。
「そーんな人ばっかりだけどなぁ。なんで?」
「会いに行こう、って思わないんですか」
「うーん」
しばらくの沈黙。
聞いてはいけないことを聞いたのかと思い、俺は心配になる。
「会いたい相手でもいるの?」
今度は俺が黙り込む。
「会いに、行きたいの?」
「……わかんないっす。会いにいったところで、どうなるんだって気もするし」
もしかしたら。
もしかしたら、相手は望んでいないかもしれない。
「目的もないのに、会いに行くのなんて、変っていうか」
「どんな相手でも、会いたいって思うのに、理由なんかいらないんじゃない」
アキラの声は穏やかだ。湖水のような静けさの中に、俺の感情を映し出す。
「それとも、会いに行くのをためらう、別の理由があるの?」
その問いに、俺は体をぎゅっと丸める。
俺の胸には亀裂があって、時折、不意に何かが入り込んでくる。
入ってこないでほしい、と願っているものさえ。
「怖い?」
「……怖いっす」
受け止めてもらえないことが。
失望することが。
無数の「ああ、やっぱり」を――
「リョータ君の家は、特殊だからね」を、
「普通じゃないから」を、
「普通じゃなくてかわいそう」を、
ずっと17年間、受け止めてきた俺自身が、
「ああ、やっぱり」
と、俺自身に思ってしまうことが。
俯いた俺を、アキラはじっと見ている。
「人間関係ってさ」
不意に、静かな声が響いた。
「惑星みたいなものだと思うんだよね」
「惑星?」
「そう。それぞれの軌道に乗ってさ、ぐるぐるぐるぐる、回ってんの。そんでさ、あるタイミングで、ほかの惑星と近づくんだよね」
「はあ」
「そのまま、ずっと一緒に近い軌道をめぐる惑星もある。一瞬だけすごく近づいて、すぐに離れてゆく惑星もある。近づいたり、離れたりするのもある。みんな、基本的にはそれぞれ、自分の軌道を回ってるだけ」
さらり、とこぼれ落ちた髪の毛に遮られて、アキラの顔はよく見えない。
「でも、大丈夫なんだ。たとえ、離れたとしてもね、同じ軌道を周り続けている限りは、またいつかきっと、巡り会うだろ」
「……それを、待ってるだけってことっすか」
「消極的に聞こえるかな」
空には、彫られたようにくっきりと畝を見せるうろこ雲が浮かんでいる。
「そんなことはないです、けど」
「だからさ、」
アキラは振り返ってこちらを見た。茶色い瞳は、昔、うちに住んでたときの、23、4歳の頃のアキラのままだ。
「会いたい、は、多分、強力な引力なんだ。たとえそれがどんな相手でも、どんな理由であっても」
何も言ってないのに、全てを見抜かれた気がした。
「近づいた、と感じたら、大事にしたほうがいい。そのチャンスを、逃さないで」
触れられたわけじゃないのに、何か、大きなものに頭を撫でられたように感じ、涙腺が緩む。
「大丈夫、きっと後悔はしないよ」
俺は立ち上がった。ジーンズの尻をぱんぱんとはたく。
「アキラさん」
「ん?」
「俺、2、3日留守にします。その間、ギャラリーの方、任せてもいいですか」
アキラさんはつかの間、目を見開くと、湯のようにふわん、と柔らかな笑みを浮かべた。
「いいよ」

「たぁーだいまーっす」
わざと、大きな声を出して、俺はコンバースのスニーカーを玄関に脱ぎ捨てる。
広い家の中には、かすかに俺の知らない匂いが漂っていて、少し空けていただけなのに、なんだかちょっぴり、知らない家みたいだ。
たんたんたん、と軽快な音がして、アキラがエプロンをつけたまま歩いてくる。
「おかえり」
「まぁた、やってたんすか、七輪」
「なんか、ハマっちゃったんだよ」
庭先に出ると、銀杏がパチパチと音を立てて、七輪の網の上で焼けていた。
湿った腐葉土の匂い。熟れた柿がつややかに光りながら枝先で揺れている。
「あーっ、腹減ったなあ」
バタン、と縁側に仰向けに寝転んだ。アキラさんはじいちゃんの半纏をジャージの上に羽織っている。なんだか昔、見たような光景だ。
「別府、どうだった?」
「もう、最高。温泉気持ちいいし、メシ、うまいし」
「……会いたい人には、会えた?」
後ろを向いたまま、なんでもないことみたいにアキラが聞いてくる。
「……なぁんか、何にも感じなかったんすよねえ」
最初にその人に会って、一番に感じたのは「あれ、なんか、思ったより小さいな」ってことだった。
別府駅に着いた俺は、ハルちゃんと合流して彼女のバンに乗り込んだ。あらかじめハルちゃんには、事情を説明していた。彼女になら、なんとなく話してもいい気がした。
「うちにコンパニオン派遣してる会社の事務所にね、聞いてみたんだ。家の場所までは教えてもらえなかったけど、電話番号は聞き出せた。で、“会わせたい人がいるので、来てくれませんか?”って伝えたら、了承してくれたの。喫茶店の前で、待ち合わせしてる」

10分ほど走り、寂れた喫茶店の前に着いた。駐車場に、女の人が立っている。
その人は申し訳なさそうに下を向いて、手のひらをこすり合わせていた。急なことに、まだ、心の準備ができていない、と言ったふうで、少し胸のあたりがちくりとした。
バンから降り、あの、と声をかける。
彼女が顔をあげた。
どきっとした。
その人の背は、俺の胸あたりまでしかなかった。
いつのまにか――当たり前だけど、俺の方が、ずっと大きくなっていたのだ。
何と言っていいかわからない。喉につかえた言葉が心臓を暴れさせ、手足をしびれさせる。
「あの」
女の人は困ったような、何かを思い出そうとしているようなぽかんとした顔をしていたが、突然、は、と目を見開いた。瞳が、表面張力ギリギリの水面のように震える。
「リョータ」
次の瞬間、彼女の二つの目から滝のように液体が溢れ出したのを見て、俺はギョッとした。彼女は溢れ出たものをこらえきれないというようにすがりついてくる。
「ちょちょちょ、ちょっと待って」

「うわあ、耳の形とかまじ似てんなとか、声の感じ、じいちゃんにそっくり、とか、本当に俺、この人から生まれたんだなあとかは思ったんすけど」
アキラは何も言わずに聞いている。
「テレビとかでやってる、生き別れた親子の感動の対面!とかって、あんなの嘘っすよ。全然、そんなん感じなくて」
サンマのいい匂いが鼻腔をつく。胃が勝手に収縮して、きゅるるる、と鳴った。
「そうかあ。そうだよなあ」
アキラの声は、立ち上る煙のように穏やかだ。
「親子だからってだけで、いちいち、感動なんてしないよな」
彼女が泣き止むのを待って、俺たちは二人、喫茶店に入った。
ボックス席で向かい合わせになり、とりあえずコーヒーを注文する。
何かを言わなければならないが、何を言ったらいいのかわからない。
その人は下を向き、鼻をすすり続けている。
あの、と言った途端に、突然、がば、と相手が頭を下げたので、俺は再びギョッとした。
「ごめんね」
下げられた頭は細かく震えている。頭頂部は少し、薄かった。つむじも、じいちゃんそっくりだな。と言っても、じいちゃんのそれは識別できないくらい、すでに薄かったけど。そんなふうに、あさってのことばっかりが思い浮かぶ。
「ダメな母親でごめんね」
自分に向かって呟くように、彼女は続けた。
「もし私がしっかりしてたら、あんなとこに置き去りにしなくて済んだのに。……あなたには、かわいそうなことをしたと思ってるの」
ぐずぐずと鼻をすする音が響く。
俺ははあ、とため息をついた。
ぼんやりしたステンドグラスのライトが、彼女の髪にまだらの光を落としている。
かあさん、と俺は言った。
この言葉を使うのは、少し、勇気がいった。
「いいんだ。俺、謝ってほしくて来たんじゃないよ。俺はただ、」
(俺はただ、
ありがとうと言いに――)
ハッとした。
そうなのだ。
なぜ、俺はここに来たのか、今、やっとわかった。
俺はこの人に、「産んでくれてありがとう」と言いたかったのだ。
どんな人生だろうと、俺は俺を、産んでくれたこの人に、ありがとうと思っている。
そのことを、わざわざ東京から飛行機に乗って、会えるかどうかもわからないまま、こうして、ここまで確かめに来たのだ。
かわいそうだとか、なんだとか、心の中で憐れまれても、それでも俺は俺のことを、俺の人生を、愛してやまない。そう、胸を張って言って良いのだと、肯定しても良いのだと、わかりたくて、ここに来たのだ。
そしてそれは、きっとここへ来る前、ずっとずっと前から教えられていたことなのだ。
じいちゃんに。
銭湯の常連さんに。
ここに暮らしたたくさんの居候たちに。
飲んだくれのおっさんたちに。
焼き鳥屋のいい匂いに、湯之谷天神の赤い鳥居に、町内会の祭り囃子に。じいちゃんがずっと守り継いできた刻の湯の、たっぷりと湯の張られた青い湯船に。
遊び疲れて眠りにつく俺にかけられた、暖かい毛布に。
はっきりとした口調で俺は言った。
「母さん、俺さ、今、幸せだよ」
その人は顔を上げて俺を見つめた。
「もちろん、こんなふうに育って、よかったのかどうかはわかんないよ。だって、他のやつらの人生なんて体験できないしさ」
かわいそうと言った女の子の目。哀れむような担任の目。透明な彼らが目の前に現れ、透明な視線で俺を刺す。
「けど、それは他のやつだって一緒なんだ。他のやつだって、俺の人生は生きられないでしょ」
「こんなふうに、育ってよかったかは、わかんないけどさ、少なくとも俺は、今、幸せだよ」
泣くほど悲しいことがあっても。他人の視線に、へこたれることがあっても。誰からも理解されない、と思うことが一年にいっぺんくらい、あったとしても。
「とりあえずは、明日死なないで、ふんばろうって思えるからさ、だから、幸せって、ことにするよ」
最後の方は言葉にならなかった。母が再び、目玉が溶けそうな勢いで泣き出したからだ。俺の目も溶けそうになり、慌てて紙ナプキンで口元を拭うふりをした。
そうして、無理やり、笑った。
そういえば、じいちゃんが死んでから、俺はしばらく、こんなふうに笑ってなかったのだ。

「会ってよかった?」
「……とりあえずは、よかったんじゃないかな、ってことで」
そこから先のことは、いろんなことがありすぎて、いちいち細かく覚えていない。母さんの家にも行ったし、今の恋人にも会った。じいちゃんの話をしたら、また、母さんは泣いて泣いて、でも、仕事の目処がついたら、すぐに東京に来てくれる、と言った。ハルちゃんちの温泉旅館に泊まって、うまいもの食わせてもらって、母さんと母さんの恋人とハルちゃんと4人で、カラオケしてはしゃいだ。
母さんちの家の洗面台に並んでいたのは、昔と同じ、青いボトルの化粧品セットだった。
「スッキリしました。俺、求めすぎてたんだなって。俺の方が、ずっとずっと強いって思っちゃったんすよねぇ。……俺が守ってやんなきゃ、ダメじゃんって」
そっか、と言ってアキラは火鉢をかき回す。
「お前はよくやったよ」
――この人の言葉は、どうして引きしぼられた心臓をふわりと解いてくれるのだろう。
不意に、涙が出そうになって、俺は上を向いた。目をパチパチして、サンマの煙が目にしみたふりをする。
親に会えたことよりも、この人の一言をもらえることの方が、なんでこんなに、嬉しいのだろう。
「俺はさ、長い間、親に会えなかったんだよね」
アキラが、静かに言った。
「……そーっすよね」
「でも、なんかさ、今は、それでもよかったって思ってるんだ」
アキラの栗色の髪が、秋の透明な風になびいている。
「その間に、俺はいろんなことを体験できた。それでいいんじゃないかって」
「そーっすね」
「家族ってなんすかねぇー」焼きたてのサンマにかぶりつきながら、俺は言う。
「相手を好きでいられることと、家族であることは、全然別だよ。……でも、それでいいんだ。自分で選んだものじゃないんだからさ、気にしなくていい」
「それぞれが、それぞれの軌道の上を回ってるんだから、」
ふわり、と笑みを浮かべて、アキラさんはこちらを見る。
「それでいいんだよ」
その瞳は、とんでもなく清々しくて、同時に冷たい色をしていて、少し寂しい、美しさだった。
「アキラさん、俺、将来どうすっかはわかんないっすけど、」
「んー?」
「とりあえず、じいちゃんが残したこの刻の湯の建物だけは、守ろうと思う。だって俺の家族はさ、この家なんだもん」
「そっかぁ」
「あ、あとさぁ」
「んー?」
「星の軌道の話っすけど、」
そのとき、生垣の向こうから、不意にバタバタと慌ただしい足音がした。
「第三者が無理やり近づける軌道ってのも、あるんじゃないですか?」
ガララ、と玄関のドアが開く音。
「アキラさんっ!?」
聞き慣れた大きな声。マヒコ兄ちゃんのやつ、きっと慌てて家から飛び出してきたのだろう。彼の表情が、容易に思い浮かぶ。ばかみたいに、息急き切って。芝犬みたいに、太い眉毛をはの字に寄せて。
俺は笑った。アキラは驚いた顔をしている。
秋の涼やかな風に乗って、七輪の煙が一筋、まばゆい秋晴れの空に向かって立ち上っていた。