
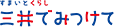
オススメ情報! 気になるバナーから詳細情報をチェック!

子どもにとって、家族の存在は大人が考える以上に大きいものだ。大人になれば、親という存在が完璧ではないことを理解するのだが、子どもからするとまるで家族が人生の全てであるように感じてしまうこともあるかもしれない。
だからこそ、家族の何気ないひと言がずっと心に残っていることは誰にだってあるのではないだろうか。それは良くも悪くもー……。

新入社員のユキちゃんはいつもニコニコしている子だった。
1年目は覚えることも多いので大変だ。当然、失敗もたくさんする。とくにユキちゃんは不器用で物覚えも悪かったので、怒られることも他の新人に比べて多かった。同じ部署の上司にも散々怒られ、嫌味も言われていたので「いつか辞めるんじゃないか」と周囲はヒヤヒヤしながら見守っていたのだけど、ユキちゃんはへこたれるようすもなく「大丈夫です! 仕事、楽しいですよ!」と元気に働いていた。
ゴールデンウィーク明けのある日のことだ。僕と同僚とユキちゃんの3人がたまたま遅くまで残業していた。ようやく仕事も終わり、なんとなく流れで「飯でも行くか」となり、3人で近くの定食屋に行くことにした。
ユキちゃんはとにかくよく食べる。チキン南蛮定食のご飯を大盛りにして、ポテトサラダも付けてモリモリと食べていた。あまりに美味しそうに食べるものだから、同僚と一緒に面白がって「好きなものをたらふく食べなさい」と勧めると、とびきりの笑顔で「いいんですか?」と言ってモツ煮込みも追加で頼んだ。
見ているこっちも幸せになるほど気持ちの良い食べっぷりだった。
それから月に何度か仕事が遅くなる日は、決まってユキちゃんとご飯を食べに行くようになった。
ユキちゃんもそれを楽しみにしてくれているようで「先輩、お腹すきました!」とニコニコと笑いながら付き合ってくれた。
一応断っておくが、別に僕はユキちゃんのことを好きだとかそういった感情はなかった。僕以外の社員もユキちゃんをよくご飯に連れて行っていたし、みんな口を揃えて「ユキちゃんとご飯に行くと幸せな気持ちになる」と言っていた。僕も全く同じ気持ちだった。
夏が終わるころには、ユキちゃんは社内で人気の後輩になっていた。みんながこぞってご飯を食べさせるものだから、入社時と比べてかなりぽっちゃりとしてきていた。そのことをからかうと、「皆さんが毎日餌付けするからですよ!」と冗談交じりに怒っていた。

暑さも落ち着いてきた9月の金曜日。その日も僕らは夜遅くまで会社に残っていた。ようやく仕事を終えると、ふたりでお決まりの定食屋に行った。いつものようにうれしそうに食べるユキちゃんの姿を見て、僕は何気なく「ユキちゃんはいつもニコニコしていて、見ているこっちまで幸せになるよ」と言うと、「え~、私ってそんなにいつもニコニコしてますかねぇ~。普通にしてるつもりなんですけどね」と答えた。
いつもは食べ終わるとそこで解散するのだが、ユキちゃんが「先輩、もしよかったら2軒目行きませんか? いいお店知ってるんです」と誘ってくれた。どんなところなんだろうと思いながら、連れて行かれたのは恵比寿の路地裏にあるBARだった。
6席しかないこじんまりとした店内には心地良いジャズが流れていた。カウンターの中からとびきりの美人が「いらっしゃいませ」と明るく出迎えてくれた。

席に着くなり、ユキちゃんがさっきの美人を「私の姉です」と紹介してくれた。
僕はびっくりした。お姉さんがいるのは前にユキちゃんから聞いたことがあったけど、こんなにきれいな人だとは思わなかったし、そもそもいきなりお姉さんのいる店に連れてこられて軽くパニックになっていた僕は思わず「全然似てないね!」と言ってしまった。
ユキちゃんは特別可愛い、という感じでも、美人というわけでもなかった。スタイルも中肉中背で、入社してから明らかに体重は増えていたと思う(その責任は僕にもあるわけだが)。
だから、カウンター越しにいる美人がお姉さんと言われたらちょっと驚いてしまう。だから、似てないなんて言ったらユキちゃんに対して失礼になってしまうのだけど、無神経にもつい口走ってしまった。
しかし、ユキちゃんもきっといままでも何度も言われてきたことなのだろう。僕の失言にも慣れっこという感じで「そうなんです、全然似てないんですよ」と笑うのだった。
その後はユキちゃんのお姉さんを交えて楽しくお酒を飲んだ。お姉さんは話を聞くのも上手だし、話も面白い。おまけに見れば見るほど美人だし、パーフェクトな女性だった。あっという間に僕はファンになってしまった。
気がつけば、終電の時間が近づいていた。ほろ酔いの僕たちは「また来ます」と言って店を出た。
帰り道、ユキちゃんは「先輩、お姉ちゃんのこと好きになっちゃったでしょ?」と言った。不意に図星をつかれた僕はどぎまぎしながら「そりゃー、あんなに素敵な女性を好きにならない男はいないでしょ?」とお茶を濁したが、ユキちゃんは意地悪な笑いを浮かべながら「先輩、残念でした。お姉ちゃんはずっと付き合っているイケメンの彼氏がいますから」と言うので僕は一瞬で失恋した気持ちになった。ユキちゃんはそんな僕の表情を読み取ってか、シッシッシと笑っていた。

それから僕らは金曜日の夜に定食屋に行った後には、必ずお姉さんのBARに寄るようになった。お姉さんに彼氏がいるということを聞いて最初こそショックを受けた僕だったけど、それはそれとしてお姉さんとユキちゃんの3人で飲むその時間が楽しかった。
何回かそんな夜を過ごしているうちに季節は冬になっていた。
その日もBARで飲んだ後、心地良い気分でゆっくりと歩いていた。ユキちゃんが「ちょっと寄り道しましょうよ」というので公園に寄った。冷える夜だったので自動販売機でおしるこを買って2人で並んでブランコに乗った。

「先輩、ずっと前に『ユキちゃんっていつもニコニコしてるよね』って言ってたことありましたよね?」
「そんなことも言っていたね~。だってユキちゃん、いつもニコニコしてるじゃん」
そう僕が答えると、ユキちゃんがおしるこをゴクリと飲んで話し始めた。
「私がまだ小さいころの話なんですけど……小学4年生の時だったかな? 母親にいきなり言われたんですよ、『あなたは顔がイマイチだから、いつもニコニコしてなさい』って」
「え? そんなこと言われたの? それはショックだね」
「はい、ショックでした。確かにショックだったんですけど……でも、小さいながらにわかっていたんです。お姉ちゃんはいつも親戚とかに『可愛い、可愛い』って言われていたけど、私はあまり言われなかったので」
「親戚もひどいね、ちょっとは気を使ってほしいな」
「でも、みんな悪気はなかったんだと思います。実際、お姉ちゃんは小さいころから本当に可愛かったので。それに先輩だって、お姉ちゃんに初めて会ったとき『全然似てない!』って言ったじゃないですか(笑)」
「あ……。あのときはごめんね」
「でも、悪気なかったでしょ?」
「うん、そうだけども」
僕が口ごもりながらそう言うと、
「全然気にしてないから。大丈夫ですから!」
とユキちゃんはケラケラと笑っていた。
「母に『顔はイマイチ』だとはっきり言われて、そのことをずっと気にしていたんですよね。……多分、傷ついたんだと思います。中学校のころとか、男子が『ブス!!』なんてふざけて言ったりするじゃないですか? その“ブス”って言葉が私に向けられたものじゃなくても、耳にしただけで、いちいちビクッとしたりしてました」
僕はなんて言っていいかもわからずに静かに耳を傾けていた。
「私は母に『いつもニコニコしていなさい』って言われてから、ずっとその言い付けを素直に守ってきたんですよ。小さいときの私って、今とは違って物静かで無愛想な子どもだったんですよ。アルバムとか見返しても、笑っている写真なんて全然ないし」
僕にとってユキちゃんはいつもニコニコしている存在だったので、笑っていない彼女を想像できなかった。
「お母さんに言われてから、最初はどうやって笑っていいかわからなかったけど、子どもながら努力して笑うようにしたんですよ。そうしたら友達もたくさんできたし、大人になった今では会社の人達にも良くしてもらって、先輩にもこうやって可愛がってもらってるし。あの日、先輩に『いつも笑ってるよね』って言われたときにちょっと複雑な気持ちはありましたけど、お母さんに感謝したんですよ。今までニコニコしてきて良かったなって」
いつものように笑顔のユキちゃんだったけど、どことなくいつもとは違う雰囲気の彼女の横顔を見ながら僕はなんて声をかけていいかわからず、空になったおしるこの缶をすすっていた。
「なんかしんみりした感じになっちゃってごめんなさい! いや、今では本当に心から笑ってますよ。無理とかしてないですから。笑ってて良かったって思ってるんですよ。まさに笑う門には福来るって感じです。だから先輩にも感謝しているんですよ! いつも可愛いがってくれてありがとうございます!」
そういう彼女はいつもの笑顔に戻っていた。
「ユキちゃんっていつもニコニコしてるよね」
何気なく発した言葉だったけど、彼女がそう振る舞うようになったきっかけが母親からのそんな一言だったとは想像もつかなかった。
「あなたは顔がイマイチだからいつもニコニコしてなさい」
それだけを聞いたら子どもに言うべき言葉ではないとはっきりとそう思う。でも、その言葉があったからこそ今のユキちゃんがあると思うと、正しかったのか、間違っていたのかわからなくなってしまう。
僕はユキちゃんのお母さんが言ったことを否定も肯定もできずに考え込んでいた。
ユキちゃんは横でブランコを勢いよく漕いで、「えい!」とジャンプしてきれいに着地して僕の方を振り返った。
「終わり良ければ全て良しですよ! 先輩!」
僕の考えていることを全て見通しているかのような顔をして彼女は笑った。

クリスマスも間近の金曜日。その一週間は特別忙しく仕事が終わったのは23時だった。
「先輩、もう定食屋終わっちゃいましたね」
「そうだね、じゃあ牛丼でも食べに行く?」
「いいですね! 大賛成です!」
牛丼屋に着くと、ユキちゃんは当然のように牛丼大盛りを頼んだ。僕も負けじと特盛りを頼んで、ふたり並んで黙々と牛丼をかきこんだ。満足したようすでユキちゃんは「ごちそうさまでした」と手を合わせていた。
クリスマスムードが漂う夜の恵比寿では、カップル達が楽しそうに歩いていた。僕たちは牛丼で満たされたお腹を叩きながらノロノロとBARに向かって歩いていた。
前に寄り道した公園の横を通ると、ユキちゃんが「ちょっと寄って行きませんか?」と言った。「いいね。またおしるこも飲む?」と聞くと「先輩、気が利きますね」といたずらに笑っていた。
誰もいない夜中の静かな公園で僕らは何を話すわけでもなく、ふたりでゆっくりとブランコを漕いだ。
「はぁー、この時間がずっと続けばいいのにな」
とユキちゃんがいきなり言った。僕も全く同じ気持ちだった。
「そうだね、来週もその次もずっとこうしていたいね」
「先輩は友達と飲みに行ったりしなくていいんですか?」
「いいんだよ、ユキちゃんと一緒にいるのが一番楽しいし」
そういうと、ユキちゃんはブランコを漕ぐのをやめて、ジッと僕を見てきた。その顔は、とても可愛くて愛くるしい。4月に彼女が入社してきたときには、ユキちゃんのことを可愛いなんて全然思わなかった。彼女の顔を見てこんな気持ちになるなんて、あのときは想像もつかなかった。
「ユキちゃんは最高に可愛いね」
「生まれて初めてそんなこと言われました」
ユキちゃんはびっくりしたような、困ったような、うれしい顔をしながらニコッと笑った。
「ねぇ、ユキちゃん」
「なんですか、先輩」
僕は一呼吸してから言った。
「ユキちゃんのニコニコした顔が僕はすごく好き。でもこれからは泣いた顔も見たいし、怒った顔も見たい。ユキちゃんの色んな顔を一番近くで見ていたい。だからずっと隣にいてくれないかな?」
ユキちゃんは僕の言葉を全部聞き終えると、ブランコをまた漕ぎ始めて、勢いよくジャンプした。振り返るとその瞳からは涙がこぼれ落ちていた。
「先輩、こんなにうれしいことってあるんですね!」
泣きながらニコニコ笑っていた。
僕たちは手を繋いでお姉さんの待つBARに向かった。お姉さんはユキちゃんの涙で赤くなった瞳を見てびっくりしてカウンターから出てきた。
ユキちゃんが泣き声で「お姉ちゃん……」と言うと、お姉さんは全てを理解したように「ユキ、よかったね」と言った。ユキちゃんはお姉ちゃんに抱きついて子どもみたいにオイオイと泣いていた。お姉さんは僕にチラリと目配せをしてきて、涙を浮かべながら笑顔を見せた。笑った顔は、ユキちゃんに少し似ているなと思った。僕はどんな顔をしたらいいかわからず、ゆっくりと会釈した。

子どものように涙を流す姿を見て、小さいころのユキちゃんを想像した。物静かで無愛想だったというユキちゃん。親から「ニコニコしていなさい」と言われたことを忠実に守ってきた、ユキちゃん。いつも笑っているというのは簡単なようでいて、とても難しいことだ。それでもずっと笑ってきたユキちゃんは、これまでどんな気持ちで過ごしてきたのだろうか。「終わり良ければ全て良し」と言って笑ったあの日のユキちゃんの顔が頭に浮かんだ。
家族から言われたことは、大人になっても案外忘れないものだ。もしもこの先、僕が父親になる日がきたら、子どもにどんな言葉をかけてあげるだろうか。どんなふうに接するのがいいのだろうか。今の僕には何が正しいのかわからない。でも、きっとその隣にユキちゃんがいたら、きっと大丈夫だ。
どんなユキちゃんも僕にとっては世界で一番可愛い。今までずっとニコニコしてきたユキちゃんの涙を見て、僕はこの子をずっと守っていきたいと思った。