
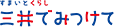


お別れは突然やってきて、すぐに済んでしまいました。
母が亡くなりました。62歳でした。
連絡を受けたのは、7月初旬の暑さの厳しい日でした。昼食を買うために会社近くのコンビニへ向かっていると、父から着信がありました。実家から連絡がある場合に電話をかけてくるのは、いつもなら母です。珍しいな、なんて思いながら通話ボタンを押し、覇気のない声が聞こえてきました。
「お母ちゃんが脳出血で倒れた。あかんかも……」
その瞬間、まだ日の高い時間帯だったにも関わらず、夜の闇に包まれたかのように目の前が真っ暗になりました。近くの公園でうるさく鳴いていた蝉の声が、やけに遠くに聞こえます。とにかく、現実感が希薄でしたね。
よくよく話を聞くと、母は今朝の8時頃、台所で倒れたそうです。救急車で担ぎ込まれた病院では未だ意識不明で、予断を許さない状況だといいます。「帰って来るなら、喪服持ってきた方がええかも」と言われましたが、「縁起でもない!」と一蹴しました。
僕は編集長に事情を話し、仕事を切り上げて新幹線で大阪へ向かいました。
車中でも、気持ちはふわふわと落ち着かないままです。よからぬ想像ばかりが頭に浮かび、そのたびに懸命に振り払いました。
けれど、悪い予感は的中しました。
病室に駆け付けると、母はすでに息を引き取っていました。久しぶりに会う姉は、母の眠るベッドのそばで嗚咽を漏らしています。父は西日の差し込む窓の外を眺めながら「喪服、必要やったな」とつぶやきました。

母の亡骸を目の当たりにしても、僕は実感が湧きませんでした。脳が現実を拒否しようとしているのか、頭がぼんやりとしてしまい、何も考えられません。
母の表情は穏やかで、わずかに微笑んでいるように見えます。しばらく待っていたら起き出しそうな気さえします。枕元に飾られているフォトフレームには、見覚えのある写真が収まっていました。僕が小学生の頃、琵琶湖畔でキャンプをしたときの家族写真です。母はまだ若々しく、「笑う門には福来る」と言わんばかりに、満面の笑みで笑っています。思えば、いつも笑顔だけは絶やさない人でした。
父は病室を出て、廊下で親族や葬儀会社など方々へ電話をかけ始めました。母との思い出に浸る暇さえなく粛々とやるべきことをする父の背中は、しばらく見ないうちに随分と小さくなっていました。
僕はいたたまれなくなり、父に車を借りてロードサイドのスーツ量販店へ行くことにしました。泣いている姉の気持ちに寄り添えないことが、ただただ申し訳なかったです。
翌日の通夜と翌々日の葬儀はしめやかに営まれました。僕はといえば、頭の中に霞がかかったようで、自分の気持ちさえ分かりかねるといった状態です。母を荼毘に付し、お骨を拾っているときでさえ、悲しみに襲われることはありませんでした。
感情が溢れ出したのは、精進落としの席でした。父が献杯のあいさつに立ったのですが、「みなさま、本日はありがとうございました」と言ったきり、次の言葉が出てきません。どうしたものかと様子を伺うと、下を向いて体を震わせています。父は声を出さず、静かに泣いていたのです。2日間気丈に振舞っていましたが、緊張の糸が切れたのでしょう。
それを見て、堰を切ったかのように涙が溢れ出しました。あまりにも突然で理解しがたかった母の死が、ありありと実感できたのです。さっとハンカチを渡してくれた姉の優しさが心に沁みました。
父は声を震わせながらあいさつを終え、会場の外へ出て行きました。背中には形容しがたい悲しみが滲んでいました。

母の死は、途方もない喪失感を僕にもたらしました。
上京してから、実家に帰るのは盆と正月くらいで、母の近況は詳しく知りませんでした。父や姉によると、特別体調が優れないというわけでもなかったそうです。
いつかしようと思っていた親孝行は、一つもできませんでした。
初婚のときは、「そのうち孫の顔でも見せられたらいいな」と夢を見ていましたが、子どもをもうけぬうちにあえなく離婚。母が「年をとったら行ってみたい」と話していたヨーロッパ旅行にも連れていけませんでした。
そういえば、しばらく母の手料理も食べていませんでした。子どもの頃から好物だった、じゃがいもがゴロゴロ入ったあのカレーも、もう2度と食べることはできません。 何をしていても後悔ばかりが押し寄せきて、仕事にもまったく身が入りませんでした。
母が生きていたら「またため息ついとる。幸せが逃げるで」と、たしなめられたことでしょう。
7月最後の土曜日、久しぶりに順子さんに会いました。順子さんは、夜は千夏ちゃんの食事を作らないといけないので、昼間にカフェでお茶をしました。
母が亡くなったことはLINEで伝えていました。順子さんは、高校生の頃に父親を心筋梗塞で亡くしたこと、あまりにも急だったので心の整理をつけるのに時間がかかったこと、苦労する母親の姿を見ていつか親孝行がしたいと思ったことなどを話してくれました。
辛かった過去を打ち明けてくれたのは、信頼されているようでとても嬉しかったですね。
順子さんは当時まだ学生だったため、親孝行らしい親孝行を一つもしないうちに先に旅立たれた、とさみしそうでした。そして、こう言いました。
「大人になると、興味のあることを見つけてやってみたいなって思っても、『今は仕事で忙しいから、いつかやろう』って一旦保留にしますよね? でも、父の死を振り返るたびにこう思うんです。本当は『いつか』なんてなくて、『今』しかないんだなって」
母が亡くなってから、自分の人生について考え込むことが多かったので、僕はこの言葉に頭をハンマーで殴られたような衝撃を受けました。今の生活において、見直さなければいけないことがたくさん浮かんできました。
そんなタイミングで、帰り際に順子さんから初めてプレゼントをもらったんです。帰宅して中身を確かめると、高価そうな一筆箋とボールペンが入っていました。添えられていたメモには、丁寧な字で「今の気持ちを書き出すとスッキリするかもしれませんよ」と書かれています。こまやかな心遣いに、凝り固まっていた気持ちがほぐれていくのがわかりました。
一筆箋を開き、握りやすいボールペンで試し書きをしてみました。紙質はサラリとしていてインク乗りも上々です。僕は久しぶりに手書きで文字を書き進めました。
まずは暮らしのこと。東京での生活は刺激的です。
けれど、長い都会生活のなか幾度となく、満員電車で訳もなく人に睨まれたり、混雑する街頭で人とぶつかって舌打ちされるたびに、何かが気持ちの中から抜け落ちていくような感覚がありました。渋谷のスクランブル交差点や新宿の大ガード下など、上京したての頃に喧騒を心地よく感じられた場所が、いつの間にか苦手になっていました。
母の死をきっかけに、一生をここで終えていいものかと自分に問いかけることが増えました。

僕が本当に暮らしてみたいのは、自然豊かな里山ではないか、と思い始めたのは四十九日も済んで少し落ち着いてきた頃でした。小学生の頃、アウトドア好きの父に連れられて楽しんだキャンプを原体験に「空気のおいしい所」で生きる気持ちよさを思い出していました。最近になってトレイルランを体験したことで、その思いはより一層強くなっていました。
もう一つは、仕事です。そもそも今の仕事は、離婚した妻と同じフィールドに立ちたいという思いから選んだものでした。クリエイティビティが求められる出版業界の仕事に、やりがいがないわけではありません。けれど、少々疲労が重なっていたのも事実でした。自分の愚行が原因ですが、人間関係にも疲れていました。
もし移住すれば、地方に住んでも東京の編集やライティングの仕事でモバイルワークができる人脈はできていました。でも、暮らしの場が自然の中に移るのならば、その場所ならではの仕事もできるのではないかという思いが浮かんできました。地元のためにコミュニティペーパーをつくれるかも、自然を相手にした仕事もしたいな、そう考えてみるだけでも新たな力が湧いてくるようでした。
順子さんは、「今は子育てがいちばん楽しい」と言います。たとえば、千夏ちゃんを連れていきたいところや体験させたいことがあったら、家計が許す限り極力実行に移しているそうです。僕も順子さんのように、自分の正直に生きたい。どこかの里山に移り住んで、季節を感じながら心新たに生きていきたい……。
母の死を経て、改めてそう思うようになりました。順子さんからもらった一筆箋には、自分でも気付かなかった、僕の人生へのまっすぐな想いがしたためられていました。

次回遂に最終回。自分の人生で本当に大切なものは何かを考え、一歩を踏み出した勇次の最後のリライフとは?