
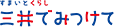
オススメ情報! 気になるバナーから詳細情報をチェック!

9月1日は防災の日。防災への備えを再確認する良い機会ですが、防災設備などは、「見たことはあるけれど、実際に使ったことがない」という方も少なくないのでは? 今回、みんなの住まい編集部は防災設備の体験ができる施設があると聞き、体験取材をしてきました。
マンションの防災について教えてもらう

今回伺ったのは、マンション管理に関する体験型コミュニケーション研修施設「すまラボ」。
三井不動産レジデンシャルサービス(株)の赤石卓己さん(以下赤石さん)に案内していただきました。
「すまラボ」は東京都職業訓練校としての認定も受けている本格的な防災体験型研修施設です。
隔壁板は意外と頑丈。どのくらいの力で蹴破れるのかやってみた
まず、赤石さんに案内されたのはこちらの隔壁板。隔壁板とは、隣接する住戸間を区切るため、隣の住戸のバルコニーとの境にある板のことです。

板の材質によって蹴破りやすさが違うのだとか。
普段は “ただの壁”と思っている方も多いかもしれません。ですが、万が一火災などが発生し、廊下に煙が充満したり、部屋に取り残されてしまったりと、残された避難経路がバルコニーだけになったときは、この隔壁板を蹴破ることで避難経路を確保できる重要な設備なのです。用途は知っていても、「実際どのくらいの力で蹴破れるの? ケガの危険性は?」など、いざというときに実行できるのか不安に思う方も少なくないのではないでしょうか。実際に、編集部スタッフが蹴破りに挑戦してみました。

「真ん中あたりを蹴ってみてください」と赤石さんに促され、えいっ! と蹴ってはみたものの、6回くらい蹴った時点でやっと小さな穴が……。ここをくぐって逃げるとなると、さらに大きな穴を開けなくてはなりません。
なかなか簡単には破れなかったため、後ろに火の手が迫っていたりしたらかなり焦ってしまいそうです。事前に体験しておくことで、どれくらい力がいるものなのかなどが把握できたので、実際に火災に遭遇した時もパニックにはならずに済みそうです。
また、蹴破った際、足が勢いよく貫通するため、反対側の壁付近に植木鉢などがあったらとても危険ということもわかりました。避難経路には物を置かない重要性も実感しました。
<CHECK!>
蹴破るにはなかなかの力が必要になる隔壁板。自信のない方や、力のない女性はかかとで後ろ蹴りをすると蹴破りやすいそう。また、物干し竿やフライパンなどで破ってもいいのだとか。サンダルでは蹴破りづらいため、ベランダにシューズを置いておくと有事の際に役立ちそうです。
避難はしごの使い方も実際に体験してみる
角住戸の場合、バルコニーの端に設けられることが多い「避難はしご」。“避難ハッチ”とも呼ばれ、はしごを使って、下の階へ避難しなければならない状況になった時に使用します。

実際に使う機会が少なく、蓋を開けたこともない方がほとんどなのではないでしょうか。
実は、いざ開けようとすると、安全のためにチャイルドロックがかかっていてなかなか開けられないのです。このロックを解除し、収納されているはしごを下ろして下の階へ避難します。隔壁板を蹴破って隣の住戸へ逃げるよりはしごを降りる方が難易度が高いため、玄関側にも、隣の住戸にも逃げられない状況になった際に使用するのが一般的なのだそうです。

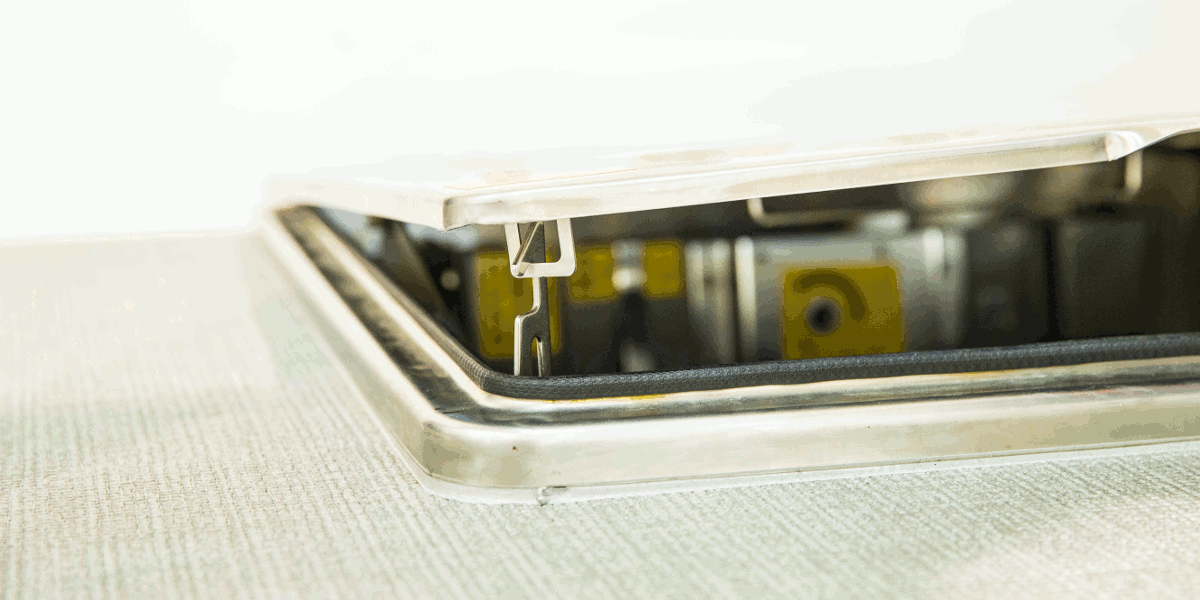
<CHECK!>
蓋を開けた後、はしごの付け根部分にあるレバーを押すと、収納されていたはしごが下りる構造。
前のめりになって手ではしごを下ろそうとすると、落下してしまう危険性があるため足でレバーを踏んで下ろすのがポイントです。
屋内消火栓は一人でも簡単に放水できるか、実際に放水!
続けて体験したのは、火災の際に使用する屋内消火栓。こちらは消防隊が使うものではなく、住民が使うための消火設備です。2名で操作するタイプの消火栓と、起動から放水まで1名で操作できる消火栓があります。
今回は1名で操作できる消火栓で、万が一の際の消火活動をタイムアタックで体験してみました。

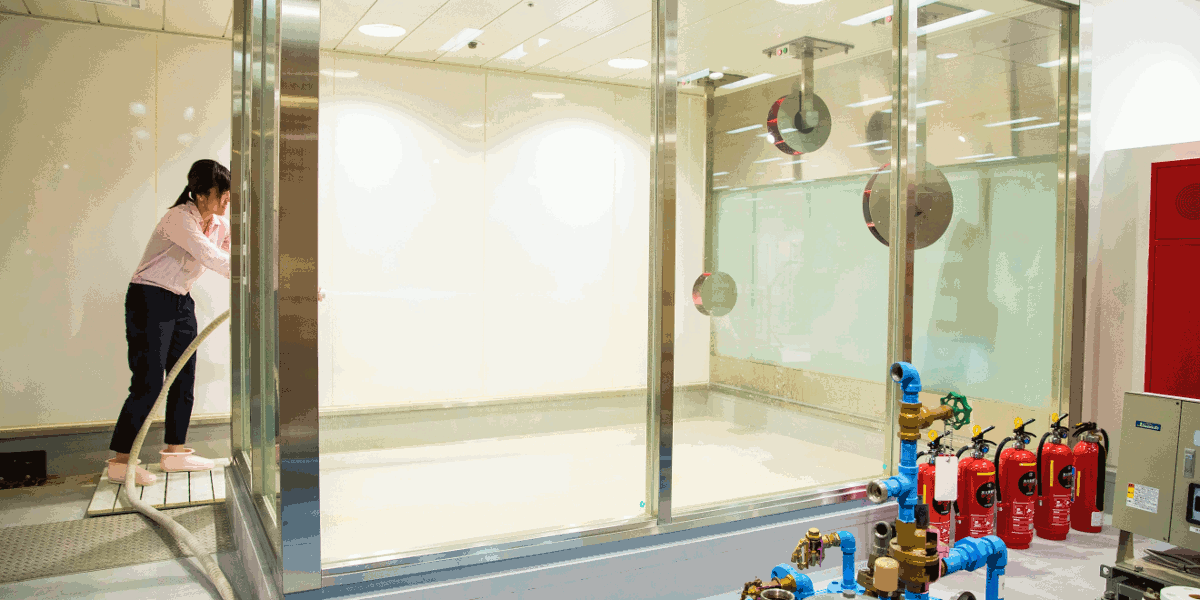
ブースの中には3つの滑車がついていて、それらを目掛けて放水し、うまく滑車が回れば滑車の上部についているランプが赤から緑になる仕組みです。
手元のノズルを回すことで放水量を調整できるのですが、始めは恐る恐る弱めの放水でスタート。ですが、まっすぐ水が飛ばず、なかなか滑車を回すことができませんでした。意を決して水量を多くし、何とか3つの滑車を回すことができました。
<CHECK!>
かなりの水圧で放水されるため、両足を踏ん張り、消火栓は両手でしっかりと持つのがポイント。
放水を止める際も勢いよく止まるため、その反動で転んだり、ノズルを手放さないように注意しましょう。
マンホールトイレやかまどベンチなど最新設備もチェック!
体験した設備の他にも、マンホールトイレの組み立て体験や簡易トイレ、炊き出し用のかまど、発電機など様々な災害対策用品も実際に見学することができました。
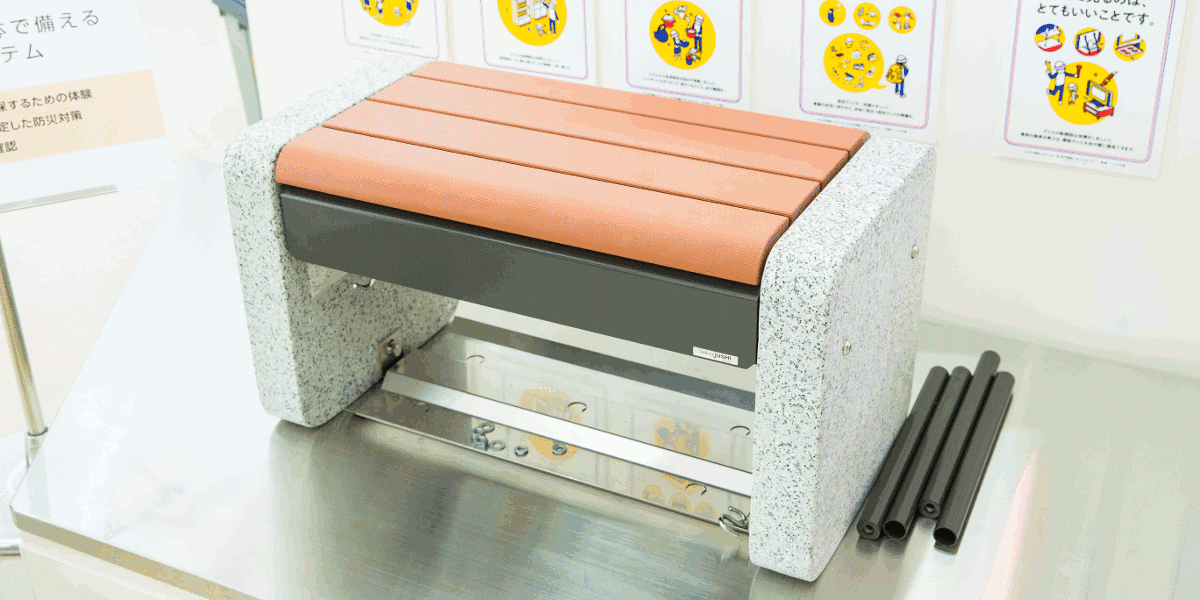
マンホールトイレは、排泄物をマンホールに直接流すためのトイレ。実際に使用する際どのように組み立てるのかを体験できます。また、マンションの外構や中庭などに設置される炊き出しができるかまどベンチの展示も。大規模のマンションに採用されていることの多い設備だそうです。

24時間、365日。常に居住者の安全を見守るため、三井不動産グループがマンション業界で先駆けて開発したセキュリティシステム「ベルボーイ」。警報発報から現地対応までの流れを実際の機器およびモニターにて確認できるエリアも。

さらに、AEDを使った救命訓練ができる他、非常ベルがどのような音が鳴るのかを体験できる展示も。音を聞いておくことにより、非常時に慌てずに対応できるようにするための設備なのだとか。実際に、編集部スタッフは聞きなれない警報音にかなり動揺してしまいました。
研修だけでなく近隣地域住民との交流の場に。「すまラボ」の設立の背景について
今回様々な防災の体験ができた「すまラボ」。こちらの施設はどのような思いで設立されたのでしょうか。
赤石さんに伺ってみました。

「すまラボは、“見て、触れて、学べる”体験型研修施設をコンセプトとした、ライフサポーター(管理人)やコンシェルジュを対象とした施設です。ハードを重視した研修施設はおそらくどの管理会社さんにもありますが、ソフト面や専有部のことを知れる施設という点が、弊社ならではなのではないでしょうか」(赤石さん)
また同施設は、東京都の職業認定訓練校の認定を受けており、三井不動産レジデンシャルサービス(株)の管理員およびコンシェルジュは5日間の研修を受講すると修了証を授与されるそうです。
自分が住むマンションにしっかりと研修を受けた管理員さんがいたら、いざというときも安心できますね。
みなさんもこの機会に、住まいの防災対策に目を向けてみてはいかがでしょうか。