
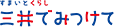

「これひとつで、人生が変わるんだよ?」
隣の席から熱心な勧誘の声が聞こえてくる。新宿の、とあるカフェではいつもこの光景を見ることができる。人生を変えたいと願う誰かのもとに、「人生が変わった」という誰かがやってきて口説き落とそうとする。もしそんなことで人生が変わるならどんなにいいか。わたしだって、東京にでてきた頃はそう思っていた。恋人を失い、住む場所を変えて、生活も変われば、何もかもが……そう、がらりと人生が変わることをどこかで期待していたのだ。
もちろん、実際はそうではなかった。
日常はだらっと続き、そのなかで緩やかに何かが変わったり変わらなかったり、進んだり進まなかったりを繰り返す。でも、いつの日か振り返ってみると、不思議なことに人生は変わっていた。きっと人は、そんなふうにグラデーションでしか変わっていけないのだ。そうわかったのは、28歳になってからだけれど。

上京をあんなに怖がっていたというのに、22歳のわたしを待っていたのは“自由”の二文字だった。実際、寂しかったのははじめの1カ月程度で、すぐに東京にも馴染んだ。上野は、“親戚のおじさん”を彷彿とさせる馴れ馴れしい街だった。店が立ち並んで賑やかで、そのいずれも敷居が低い。昼でも夜でも誰かが飲んでいて、誘い込まれる。会社も堅苦しい雰囲気ではなく、少ない同期にも無事恵まれた。先輩を含め、仲間たちはわたしを「スミー」と呼ぶ。皆、とくに意図はないはずだが、わたしはその名を聞くたび、どうしても『ピーター・パン』の中に出てくる、フック船長の手下の名前を思い起こす。おっちょこちょいで、人情味深いスミー。あんなふうに、なれたらいい。そんな願望もこめて、スミーというあだ名が好きになった。
住んでから数年経つと、上野のことはすっかりわかるようになった。仕事終わりに行く安い居酒屋には困らないし、気持ちのいい公園も、定期的に展示の変わる博物館も、フィットネスジムだってある。部屋のダンボールがすっかりなくなるころには、仕事終わりにヨガに通う……というOLの夢を叶えていた。
仕事が終わって20時にはヨガへ行き、帰ってからは安いスーパーで買った食材で料理をする。ざっと炒めて完了、というものがしばしばだったが。コト、と皿をテーブルに置き、スマホを片手にいただきます、とつぶやく。ひと口食べる前から片手ですばやく文字を打ち込む。日課である食材の「効果・効能」を調べるためだ。
「パプリカ 効能」で検索をすれば、パプリカが美肌効果をもたらす食材であることがすぐにわかる。「これは、美肌効果がある」。そう言いながらパプリカをひと口たべる。これが上京して身についた、わたしの日課だ。きれいな黄色のパプリカは、火を通した方がビタミンの吸収がよくなると知ってからは、かならず炒めた。ひと口噛むたびに、あまい味わいをしっかり感じる。そうしてもう一度「美肌効果」と唱えると、それらはみるみるうちにわたしの顔や手に広がって、栄養を届けてくれるような気がした。ぐんぐんと美肌になっていくようなイメージだけをいつも思い浮かべる。鏡をみても、なにひとつ変わらない自分がいるだけなのだけれど。それでもよかった。ヨガにせよ、料理にせよ、自分のためになにかをしているというそのことが、わたしを満ち足りた気持ちにさせてくれたから。
カズヒロと別れたわたしは、支柱を失った朝顔のようだった。ぐったりと倒れ、どちらへ伸びたらいいのかがわからなくなっていた。けれど、ゆっくりゆっくりと上野の空気を吸って立ち上がっていった。空気を、人を、会社を、街を、支柱に変えて。雑然としている上野の大地は、わたしに安心を与えてくれ、いつのまにかすっかりとひとりでいられるようになっていた。ひとりでも、たのしい。そのことが、どれだけ誇らしいことか。わたしは、嫌という程ひとりですごした。そのたび、自分がひとりでも楽しめることを嬉しく思っていた。