
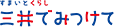

誰かと一緒にいなくちゃいけない。あのころは、そう思っていた。そうじゃないと、自分の価値が保てないような気がした。親ほどわたしを愛してくれるひとが近くにいない。それがこんなにも足元をぐらつかせるのだと、高校生の頃は知らなかった。福岡の大学に進学したのを機に親元を離れ、急にひとりぼっちになったわたしを肯定してくれたのは、"休日の予定の数"だった。誰かといれば、わたしは愛されているのだと思えて、友達をたくさん作ってはどこかの誰かに「わたしの人生は輝いています」と見せつけるのに必死だった。
たいして好きでもない友達と集まり、たいして好きでもない時間を過ごしては、写真だけはやたらとたくさん撮ってネットにアップした。地元の友達が見てくれているといいなと願いながら。
夏になればみんなでバーベキューをして、冬になればスノボへ行き、たくさんの笑顔の中で笑ってみせた。友人から愛されている、わたし。「そんな空虚な見栄は、ばかげている」なんて当たり前のこと、言われなくてもわかっている。そんなのが"本当に大事なものじゃない"とも。それでも、わたしはそうするしか方法を知らなかった。
だから、わたしがカズヒロに会ったとき「これだ」と思った。これこそが、わたしが"本当にほしかったものだ"、と。たくさんの友人に囲まれることなんかじゃなくて、大事な人と一緒に過ごすことが必要だったんだ。もう誰かといることに必死にならなくていいんだ、と。

福岡は、狭い。学外での飲み友達はすぐにできる。カズヒロと出会った日のことは、忘れもしない。あれは大学4年になってすぐのことだ。友達が、友達の友達をたくさん連れてくるような80人規模の大きなお花見に参加した。そのとき、たまたま隣に座ったカズヒロがこう聞いてきたのだ。
「これ、本当にたのしい?」
まっすぐな目で、心から不思議そうな顔つきで。
「スミレちゃん? だっけ? スミレちゃんは、こういうのがたのしいの?」
「え、いや、たのしいっていうか」
「じゃあなんで来てるの?」
「え、いや……」
わたしが口ごもったのは、"考えたこともなかったから"だ。この飲み会がたのしいかとか、この人たちが好きかとか。はたまたこの飲み会に意味があるかとか、どうして参加しているかとか。むしろ、そんなことを考える人がいることに驚いた。
「時間が……あったから?」
そう答えると、カズヒロは大笑いして「どっか行こうぜ」と、わたしの手を引っ張った。二人でブルーシートから立ち上がって、靴を履いている間、誰も「どこへ行くの?」と聞かなかった。というよりも、みんなお酒に夢中で、わたしたちの姿なんて見えていないようだった。ユウコもミユもマサトもカッチャンも、みんなみんな、淡いベールの向こう側にでもいるように、わたしたちに気づかなかった。わたしもお酒が回っていたのかもしれないけれど、目の前がかすんできて、もしかして今まで見ていたものは夢だったのかもしれないと思った。
リズムの良いコールと大笑いしている声を抜け出してから、やっと「桜が綺麗だ」と気付いたとき、わたしはあんな場所は好きじゃなかったのだと、初めて知った。
カズヒロの手のひらはじんわりと熱く、「時間があるなら、海見に行こうぜ」と微笑まれた。「行こうぜ」、なんて東京の人みたいな口調。このひとは東京出身なのかな、とぼんやり思った。そうして桜が葉桜になるよりも早く、わたしたちはすぐに関係を持ったのだった。