
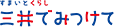


「ベタだねえ、どこまでも、ベタだねえ」
彼女は皮肉を言いながらも、やたらと上機嫌だった。
港区・六本木。ザ・リッツ・カールトンに入っているレストランで夕食を終えると、エントランスに停まっていたタクシーに飛び乗った。ふたりで1本空けたモエ・エ・シャンドンが、心地よく脳を揺らしている。

青色の発光ダイオードで彩られた通りを抜ける。大きな交差点に差し掛かると、出会って早々に腰に手を回す黒人男性と、若さを一番の売りにしたような女性が信号待ちでキスをしていた。その前を通過し、次の目的地である東京のランドマークを目指して車は進む。
「なんでさあ、東京タワーが、東京の中心みたいなんだろうね?」
窓越しに微かに見えた、赤いてっぺんを眺めながら彼女が尋ねる。
「スカイツリーの方が、高さもあるし、新しいじゃん。もう主役はそっちになってもいいのに」
「んー、色じゃない?」
僕は適当に答えを考える。
「色?」
「戦隊モノの主人公は、いつだって赤だから」
「ああ、なるほど?」
彼女を納得させたことが、少しだけ誇らしかった。
今日は、最後まで自分のペースでいたい。付き合って4回目の記念日。この日に彼女にプロポーズすることを、半年前から虎視眈々と企んでいたからだ。たとえそれが彼女にバレていたとしても、僕はプロポーズをする男性として、毅然とした態度でいたいと思っていた。
切り出したのは、先月の日曜だった。

2年住んで慣れ親しんだ高円寺の1LDK。彼女の作るスクランブルエッグに、レタスとトマトのサラダ、僕が見つけてきた精肉店の生ハムに、ローソンで買ってきた惣菜パン。「たまには朝食らしい朝食を」とふたりで話した末に揃えた料理を、ダイニングテーブルに並べたところだ。
「今度の記念日だけど、ホテルのレストランとか、どう?」
少し遠慮がちに切り出したのは、これまでの記念日デートにおいて、僕があげたプランが通ったことはほぼほぼなかったからだ。
箱根旅行を提案した結果、ディズニーランドになった一年目。星野リゾートでお泊まりを提案したところ、沖縄旅行になった二年目。自宅で過ごそうと言ったのに、オーストラリアに行った三年目。いつも彼女の修正案に僕が折れた。
そもそも“記念日に行きたい場所”なんて、僕にはそんなに願望がなかった。お互いが彼氏・彼女であることを再認識できる日であるならば、場所はどこだって関係ない。これは負け惜しみでも何でもなく、本音の本音だ。
でも、4回目の記念日を迎える今回ばかりは、どうしても自分の意思を通しておきたかった。プロポーズのシチュエーションは、結果に大きく左右すると思っていたからだ。
「ああ、ベタだけど、いいかも。都内のホテルってことだよね? リッツ・カールトンとか?」
返事は、意外なほどあっさりと返ってきた。過去の経験を考えてみても、ここまであっさりと決まったことは初めてだった。ところが、さらに驚いたのは、次の彼女の一言だ。
「そこで、プロポーズかな」
コーヒーを噴き出しかけた。冗談で言っているのか、脅迫のつもりなのかよくわからない。ニヤニヤとこちらを見つめながら、彼女はそう言った。
「まあ、そうかもしれないね」
早々に見透かされたことに動揺しながらどうにか濁そうとするが、もう遅い。
「そっかあ、私たちも、結婚かあ」
うれしそうだった。大きく伸びをしながら、満足げに彼女は言う。これでは当日のサプライズも何もない。むしろ、既に彼女も結婚するつもりになっていることがビシビシと感じられた。それは、つい2~3年前の彼女だったら考えられないことだった。あれほどドラマチックで可憐に生きることを望む人が、プロポーズに関してここまでドライだとは、正直驚いた。
「場所はどこでもいいよ。楽しみにしてる」
「プロポーズするとは一言も言ってないけどね?」
「はいはい、わかりました」
洗い物の食器を重ねる音すら、どこか陽気な音楽に聞こえた。
ドラマチックでもなんでもないシーンなのに、僕にはそれが極上のクライマックスシーンのようにも思えた。

タクシーが夜の東京タワーに到着すると、僕らは展望台を目指した。
東京に越してきてからというものの、彼女も僕も東京タワーにのぼったことは一度たりともなかった。「そんなこと言って、どうせほかの女と来たことあるんでしょ?」と疑ってくる彼女を軽くかわしながら、展望台へ向かうエレベーターが目的地へ着くのを待った。
独特の音とともに扉が開くと、視界が一気に開けた。
ここ最近は不安定な天気が続いていたが、見事なまでに澄み渡った空だった。僕らが東京で見た景色の中で、一番きれいな光景が目の前に広がっていた。
それは、自由が丘駅を見下ろすカフェから眺めた街並みよりも、高円寺のさびれた公園から見た空よりも、何倍も何十倍も東京らしい光景だった。

「あのさ」
「うん」
目の前に広がる景色に圧倒されている彼女に、少し早いと思いつつ、切り出した。
「プロポーズしていい?」
もうするの? という顔をされると思ったが、彼女は彼女で、このタイミングが嫌いじゃないみたいだった。
「確認取るって、新しいね」と言いながら、少し距離を離して、僕の正面に立った。
「もしも『ダメ』って言ったら、どうする?」
「そうだな、とりあえず帰りは、階段で帰ってもらう」
「思ったよりキツいなあ」
ケラケラと笑った。この空気が好きだった。サプライズとか、僕には向いていないし、きっと狙っていっても、失敗する。それを見越してか、ドラマチックで可憐に生きることを望む彼女だって、この場だけは見栄を張らないようだった。
「いいよ、聞かせて?」
彼女は、いつもの見透かすような瞳で僕を見つめる。
「ベタなセリフでごめんなんだけど」
それでいいよと言うように頷く。
「ずっと大切にするから、僕と、結婚してください」
最後まで言い切れたのか、わからない。彼女は胸に飛び込んできて、痛いぐらいに抱きしめた。
「お願いします」
その声で、泣いているのがわかった。
何の変哲もない男の、何の捻りもないプロポーズに涙したことを、悟られたくなかったのかもしれない。彼女は僕と絶対に目を合わせぬよう、腕にさらに力をかけた。
僕は彼女の頭を撫でながら、胸ポケットにしまっておいたハンカチをそっと握らせる。
彼女は胸元で涙をぬぐいながら、グズグズと音を立てて言う。
「ハンカチなんて、いつも持ってないじゃん」
「ハンカチは、女性が泣いたときに差し出すためにあるって、ロバート・デ・ニーロが言ってたから」
「それ、『マイ・インターン』のシーンじゃなかった?」
「正解。嫌いな映画だったよな」
「その台詞だけは、好きだった」
「ホント? でも、本当に伝えたかったのはそこじゃなくて」
「うん?」
濡れたばかりの瞳に、焦点を合わせる。
「初デートのことだって、きちんと細かく覚えてるからって、言いたかった」
できるだけクールに、落ち着いたトーンで、前もって考えてきたセリフを伝えた。後半、頬がひきつる感覚が残った。つくづくこういうセリフが似合わない。
「口説き文句が、キザすぎる」
彼女は、泣きながら笑った。
僕もそれにつられて、涙腺を緩ませた。
「ドラマチックが好きだってわかってるから、格好つけたのになあ」
すぐにでも笑いに変えないと、恥ずかしくてその場から逃げ出しそうだった。
「プロポーズって、それだけで十分ドラマチックだよ。演出する必要なんて、これっぽっちもないよ」
それは正論のようにも感じたし、フォローしてくれているようにも思えた。
「飾らずまっすぐ届けてくれるのが、この世で一番素敵だよ」
その笑顔が、出会って5年経っても、愛おしかった。
「あーもう、今のでますます結婚したくなった」
「バーカ」
笑う彼女と、その後ろに広がる東京の夜景が、一枚の画のようだった。
ロバート・デ・ニーロの台詞を忘れても、この景色だけは忘れないと決めた。

「引っ越すなら、どこがいい?」
帰りのエレベーターで、僕は尋ねる。
「今度こそ、中目黒かな」
涙を引っ込めた彼女は、じっくり考えた末での結論とばかりに言った。
「じゃあ、今度は14万円上限で」
「お、私たちも、出世したねえ」
ふたりして、笑う。
東京の象徴の麓から、僕らの新居探しが、再び始まった。
おわり